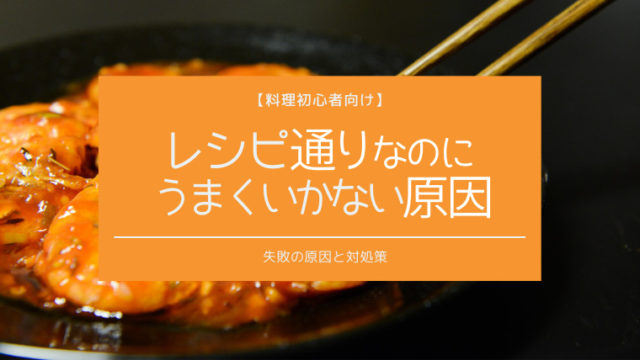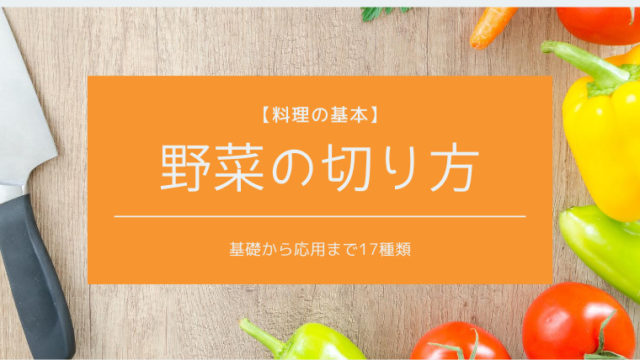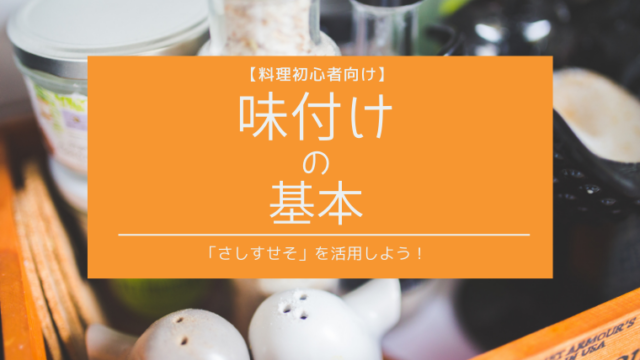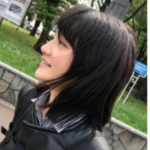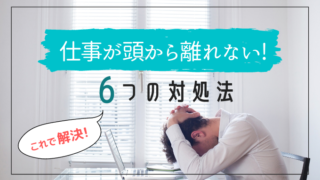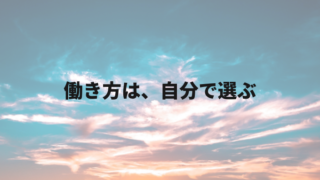この記事では、野菜の選び方と保存方法について紹介します。
野菜には賞味期限が載っていないですし、どのように選んで保存すればいいのか迷ってしまうことがよくあります。
私自身、料理初心者の頃にすぐに使わない野菜をダメにしてしまった経験が何度かありました。
野菜別に鮮度の良いものの選び方や保存方法を理解すれば、食材を美味しい状態で使うことができますよ!
まずはよく使う野菜から少しずつ覚えていくのがおすすめです。
contents
野菜の保存でよく使う道具
キッチンペーパー・新聞紙
キッチンペーパーは脂を吸い取ったりする用途以外にも、食材の保存に役立ちます。
新聞紙があれば経済的です。
どちらも、食材を保存するときに通気性をよくしたり、乾燥と湿気を防いでくれます。
野菜を冷蔵庫で保存するときに注意したいのは、水分の蒸発と湿気です。
乾燥が苦手な野菜は、濡れたキッチンペーパーか新聞紙でくるんだ上で、ポリ袋に入れると鮮度が保たれます。
また、水分を苦手とする野菜は乾いた新聞紙で包み、ポリ袋に入れて保存することで、キッチンペーパーか新聞紙が余分な水分を吸収してくれますよ。
また、新聞紙の場合は、日光が当たらないようにしてくれる役目もあるので、じゃがいもの保存などに使われることがあります。
チラシは素材が違うので代用は難しいです。
ジップロック
冷蔵保存用、冷凍保存用(フリーザーパック)の種類があり、野菜の保存に使えば野菜の乾燥や酸化を防いでくれます。
サイズはMとLが便利です。
きのこやピーマンなどの小さい野菜を保存すにには、Mサイズを(大体1パックでMサイズに入ります)。
ネギなど、切っても長さが必要なものにはLサイズが便利です。
枚数はMサイズの方がよく使うので最初はMサイズ10枚、Lサイズ5枚くらいを目処に揃えるのがおすすめです。
自分がよく使う食材に合わせて徐々に増やしていくといいと思います。
ビニール袋(ポリ袋)
ジップロックほどは密封してなくてもいいときに使います。
スーパーでよくある透明の袋や小さめの手持ち袋が便利です。
スーパーで使ったものを使用する場合は、肉類や魚類で汚れているものは避けましょう。
私は毎回保存の際に適した大きさをストックから探すのに時間がかかるので、100均で程よい大きさのものを購入して使っています。
野菜の選び方と保存方法
トマト
トマトの選び方
全体の色が均一で皮にハリがあり、ヘタの緑色が濃く、ピンとして新鮮なものを選びます。
へたがしおれていたり、黄色っぽくなっているものは鮮度が落ちている証拠です。
また、ずっしり重いトマトのほうが糖度も高いです。
賞味期限
冷蔵庫で保存したトマトは、10日程度が保存期間。
傷や凹みがあるものは1日〜2日しかもたないので、優先的に食べましょう。
時間が経ってやわらかくなったトマトは、加熱してソースとして使えば美味しく食べられます。
保存方法
青いトマトはあえて常温保存することもありますが、赤いトマトは冷蔵庫の野菜室で保存しましょう。
冷蔵庫で保存する場合は、トマトのヘタを下にします。
保存するときはお皿やパックに並べて、しっかり口を閉じてください。
買ったときのパックのまま保存しても大丈夫です。
レタス
レタスの選び方
芯が白く、切り口が2cm(十円玉)ほどの大きさで、葉がみずみずしいものを選びましょう。
芯の高さのあるものは、伸び過ぎていて味も食感も悪くなるので避けます。
また、葉の巻きがゆるやかで、持った時に軽めのものを選ぶことがポイントです。
重いものは育ち過ぎて葉が固かったり、苦味が出てしまっている可能性があります。
サニーレタスやリーフレタスなどの結球しないタイプは、葉先が色濃くパリッとしたみずみずしいものを選びましょう。
賞味期限
レタスは、水分量が多いので日持ちする野菜ではありません。
鮮度が落ちると苦味が強くなります。
使い切る目安は1週間です。
保存状態かがよければ2週間ほど持ちますが、早めに使い切ってしまったほうがいいでしょう。
保存方法
レタスは芯を濡らしたキッチンペーパーで包み、玉のまま保存します。
キッチンぺーバーが乾いたら、新しいものに取り換えるようにすると1週間程度新鮮さが長持ちします。
包丁で切ると金属と反応して酸化が進んでしまうので、使う分だけちぎって食べるようにしましょう。
外側の葉は、食べるときにむきます。
きゅうり
きゅうりの選び方
きゅうりは曲がっていてもいいので、太さが均一なものを選びます。
へた側と逆のほうが太くなっていると、水分が下にたまってきている証拠です。
太さがあるものはス(空洞)が入りやすく、みずみずしさがなくなるので注意しましょう。
また、へたと反対の側には残留物がたまりやすいので、調理する際は厚めに皮をむきます。
全体が緑色で艶があるもの、へたの切り口がみずみずしいものは鮮度がいいです。
イボがある種類のものは、いぼがしっかりあるほうが新鮮なので選ぶ際の参考にしましょう。
賞味期限
冷蔵庫で保存した状態で、1週間が目安です。
保存状態がよければ、10日前後が賞味期限になります。
保存方法
きゅうりは乾燥と湿気を防ぎながら、野菜室で立てて保存しましょう。
水分が多い食品なので、乾燥した環境ではすぐに水分が抜けてしまいますが、一方で湿度が高すぎても水分が付着して腐りやすくなります。
また、きゅうりや大根のなどの野菜は、縦に伸びようとしてエネルギーを消費するので、横にして保存すると余計に糖分や水分などを消費してしまうそうです。
その分しおれるのも速くなるので、立てて保存するようにしましょう。
また、きゅうりはもともと温かいところで栽培されるもので、低い温度で保存すると低温障害を起こしてしまいます。
きゅうりにもっとも適した温度は10~13℃なので、野菜室で保存するようにしましょう。
新聞紙またはキッチンペーパーできゅうりを包み、ポリ袋にいれて保存します。
密封した環境では、きゅうりから放出された水分の逃げ場がないので、ポリ袋は密封せずに口を開いておくのがおすすめです。
玉ねぎ
玉ねぎの選び方
玉ねぎは持ってみてずっしり重みを感じ、かたく締まっているもののほが水分が保たれていて美味しいです。
頭部から痛むので、首と根の部分が小さくぎゅっと締まっているもの、表面の茶色い皮がしっかりと乾燥して艶があるものを選びます。
できるだけ表面に傷がないものを選びましょう。
新玉ねぎの場合は、上の部分を軽く押して柔らかいものは中が腐っている可能性があるので避けます。
賞味期限
皮つきの場合は、常温保存で2ヶ月もちます。
保存方法
玉ねぎは湿度に弱いので、小分けに新聞紙かキッチンペーパーで包んで湿気を防ぎます。
半分に切った玉ねぎは、ラップにつつめば冷蔵保存で1〜2週間くらいもちますが、切り口か痛むので早めに食べましょう。
スライスした玉ねぎの場合は、もっと賞味期限が短いので注意が必要です。
スライスしたものは、ラップで包みタッパーか保存用袋に入れて保存します。
通常玉ねぎは常温保存が適していますが、新たまねぎは水分が多いので常温で保存すると皮がぬめっとしてきます。
そのため新玉ねぎの場合は、冷蔵保存しましょう。
湿気対策のため、新聞紙で包んでポリ袋に入れ、冷蔵庫で保存すれば1週間持ちます。
湿気が苦手な新玉ねぎは、野菜室ではなく、冷蔵庫内で保存するのがおすすめです。
ネギ
ネギの選び方
根深ネギ(長ネギ、白ネギとも呼ぶ)は、全体的にみずみずしいもの、白い分部分と青い部分の境目がはっきりしているものを選びましょう。
また、白い部分は巻きがしっかりしていて固いものが新鮮です。
青ネギ(葉ネギ、万能ネギともいう)は、葉先までピンとしてハリがあるものを選ぶのがポイントです。
賞味期限
冷蔵保存で1週間が目安です。
ねぎは1週間をすぎると繊維が多くなるので、1週間以内に食べ切るのがおすすめです。
保存方法
長ネギ(白ネギ)の保存温度は0~2℃なので、冷蔵庫で保存します。
冷蔵庫ではネギを新聞紙で包み、ビニール袋に入れて立てて保存しましょう。
葉の部分を切り、立てれる長さに切っておくのがおすすめです。
青ネギ(葉ネギ・万能ねぎ)の場合は、新聞紙を少々湿らせておくことで、より日持ちします。(保存期間や同じく1週間です)。
刻んで冷蔵すれば3〜4日、冷凍すれば1ヶ月は日持ちします。
冷凍のまま料理の仕上げにかけたりすることができるので、おすすめの保存方法です。
アボカド
アボカドの選び方
アボカドは熟すにしたがって皮色が緑から黒へと変化します。
すぐに食べたい場合は、皮が黒いものを選びましょう。
選ぶ際は、皮にツヤとハリがあり程よく弾力のあるものを選びます。
脂肪分の少ないものは、さわると皮が浮くので気をつけます。
ヘタの部分から熟すので、さわってみて過度に柔らかいものは酸化していることがあるので避けましょう。
2〜3日後に使いたい場合は、あえて食べ頃一歩手前の濃い緑色で、わずにかに柔らかいものを選びのがおすすめです。
アボカドの賞味期限は?
熟したアボカドは冷蔵保存で3〜4日です。
アボカドの保存方法
アボカドは元々暖かい場所で育つものなので、熟さない緑色の時期は常温保存にしましょう。
食べ頃になるまで風通しのいい、日の当たらない場所で保存します。
適正温度は20度前後の室内です。
27度以上の気温が高い環境では避けましょう。
茶色で周りがやわらかなくなっているものは、冷蔵庫の野菜室で3〜4日保存できます。
4度を下回る場所で冷蔵すると、低体温症を引き起こして黒い斑点ができ、見た目が悪くなったり、筋が多くなって美味しく食べれなくなるので注意が必要です。
日もちさせたい場合は、ラップか濡れた新聞紙で包み、保存袋に入れてから野菜室で保存しましょう。
アボカドに黒い点や筋があるときは食べれる?
アボカドを切ってみたら、黒い点や筋がありびっくりしたことがあります。
調べてみると、これは腐っているのではなく、アボカドの種に栄養素や水分を送る維管束と呼ばれるものが身に比べる酸化しやすく、その結果黒く変色しているだけとのことでした。
黒い筋があっても、アボカドの身自体が黄緑色をしていれば食べても大丈夫です。
全体が黒い場合や変な臭いがしたり、切った時にすぐに崩れるくらいやわらかい場合は腐っている可能性があるので、食べるのをやめましょう。
スーパーで安売りの値札がついているものは熟している状態が多いので、早めに食べることも大切です。
にんじん
にんじんの選び方
にんじんはみずみずしく、全体的に丸みがあるもの(ふっくらしているもの)、細かいひげが少ないものを選びましょう。
表面が滑らかで、赤みが強いものは新鮮です。
赤みが強いほど、カロテンが多く含まれます。
茎の切り口は小さいものが甘味が強く良いにんじんです。
袋詰めで売られているにんじんを選ぶ時は、袋に水滴のようなものが付いていないか確認しましょう。
水分が無く、乾燥気味のにんじんは鮮度の問題があり、味が悪い場合が多くなります。
賞味期限
冷蔵保存で1ヶ月持ちます。
カットしたにんじんは3〜5日が目安です。
保存方法
他の野菜に比べて保存がきくにんじんは、湿気と乾燥から守って保存することが大切です。
新聞紙かキッチンペーパーでくるみ、ポリ袋に入れて立てて保存しましょう。
カットしたにんじんは、ラップでしっかり包んで保存します。
切ったところから傷みやすいので、早めに使うようにしましょう。
葉がついている場合は、栄養を奪われてしまうので切り落とします。
じゃがいも
じゃがいもの選び方
じゃがいもは皮が薄く、凸凹が少ないもの、表面がなめらかで全体的に形がふっくらしているものを選びます。
中玉くらいのもの、しっかりとした固さがあるものが良いじゃがいもです。
芽が出始めたり、しみや緑色になっている部分のあるものは避けましょう。
新じゃがいもの場合は、表面の皮が薄く、指ではがれそうなくらいの物が良いです。
古くなるにつれて皮が厚くなり剥がれにくくなります。
賞味期限
常温で置いた場合、夏場は約1週間、冬場は約1~2ヶ月保存できます。
冷蔵保存では水分も抜けやすくしわしわになりやすいので、1週間を目安に食べ切りましょう。
切ったじゃがいもは、冷蔵保存で約2日です。
切ったところから痛むので、早めに食べ切りましょう。
保存方法
じゃがいもを保存する最適な温度は、7度〜20度です。
湿気や光に弱いので、風通しのよい冷暗所に置くのがよいとされています。
直接日光が当たらないように、新聞紙に包むか、紙袋に入れて保存しましょう。
新聞紙などで包むと、通気性がよくなる効果もあります。
冷蔵保存の場合には、新聞紙で包んでポリ袋に入れ、湿気がたまらないように軽く閉めて保存しましょう。
切ったじゃがいもは、空気に触れるとでんぷんやポリフェノール色素が酸化して表面が変色してしまいます。
カットして食べきれなかった場合は、ひたひたの水を張ったタッパーにじゃがいもを入れて、空気に触れないようにしっかり蓋をして冷蔵庫で保存しましょう。
長時間水に浸すと栄養分が流れたり味も悪くなってしまうので、できるだけ当日中に食べ切るのがおすすめです。
長いも
長芋の選び方
皮が薄くてハリがあり、傷や斑点がなくきれいなもの、凸凹が少なく手に持ったときに重量感があるものを選びましょう。
また、切り口が変色しておらず、白くみずみずしいものが新鮮です。
ひげ根やひげ根の跡が多いものは、粘りが強いとされています。
賞味期限
カットされた長芋の場合で、野菜室で1週間持ちます。
保存方法
切って売られている長芋の場合は、切り口をサランラップでしっかり包み、冷蔵庫の野菜室で保存します。
この方法で、1週間くらいの保存なら美味しく食べれます。
切り口は茶色く変色しますが、切り捨てて調理すれば大丈夫です。
ごぼう
ごぼうの選び方
太さが均一でまっすぐでひげ根が少ないもの、切り口にす(穴)が入っておらず、黒ずみがないものが美味しいごぼうです。
柔らかくぐにゃぐにゃと曲がるものは避けます。
ごぼうは乾燥しやすいので、新鮮さや風味を保ちたいなら泥付きを選びましょう。
洗いごぼうの場合は、表面のきめが細かく、ひび割れがないものを選ぶのがポイントです。
賞味期限
常温保存
土ごぼうの場合は、冷暗所の保存で1〜2週間ほど持ちます(冬は1ヶ月以上)。
新ゴボウは、鮮度が落ちやすいので3~4日が目安です。
夏場の気温が高い場所での保存は適していません。
冷蔵保存
洗いごぼうやカットしたごぼう、下処理済みのごぼうは冷蔵保存で3~4日程度です。
冷凍保存
カットしたごぼう、下処理したごぼうを冷凍保存する場合は約1ヶ月持ちます。
時間の経過とともに鮮度は少しずつ落ちていくので、おいしく食べるには2週間が目安です。
保存方法
常温保存
常温保存する場合は、土付きのままで新聞紙にくるんで乾燥しないようにし、冷暗所で保存しましょう。
根を下にして、立てるように保存します。
長すぎて保存が難しいという場合は、適当な大きさに切ってから保存することもできます。
ごぼうをカットする場合は、切り口から水分が蒸発することを防ぐことが大切です。
切り口が空気に触れないようラップでしっかりと包んでおきましょう。
冷蔵保存
ごぼうを冷蔵保存する場合は、保存しやすい適当なサイズにカットし、湿った新聞紙でごぼうをくるんで、保存容器や保存用袋に入れましょう。
湿った新聞紙を使うのは、ごぼうをできるだけ乾燥させないためです。
乾燥すると美味しさが損なわれてしまいます。
ごぼうは下準備も兼ねてささがきなど、スライスしてから冷蔵保存する方法もあります。
この場合は保存容器に酢水を入れてその中で保存しますが、長期保存には向いていません。
できるだけ早く消費するようにしましょう。
冷凍保存
すぐに使わない場合は、アク抜きした後にキッチンペーパーで水分をよくふき取り、保存用袋などに入れて冷凍庫で保存しましょう。
解凍せずにそのまま煮物や汁物に使えます。
冷暗所とは?
冷暗所とは直接日光が当たらない風通しがよい場所、湿気の少ない場所のことで、温度は14度以下の環境をいいます。
夏場は外気の温度が高いので冷暗所を確保することは難しいので、冷蔵庫で保存しましょう。
キャベツ
キャベツの選び方
春キャベツの場合は、芯の切り口が小さく、巻きのゆるいものを選びましょう。
また、葉が鮮やかなグリーンで全体にツヤとハリがあるものがおすすめです。
一方、冬キャベツは巻きがしっかりと詰まっているものがベストです。
持ったときにずしりと重く、かたいものを選ぶようにします。
賞味期限
キャベツを丸ごと保存する倍は、芯をくりぬき、ぬらしたキッチンペーパーで包みます。
ポリ袋入れて保存すれば、2週間持ちます。
キッチンペーパーは乾燥したら取り換えるようにしましょう。
カットしたキャベツの場合は、ラップに包んで野菜室で3~4日ほど持ちます。
保存方法
玉のキャベツの保存
キャベツは芯に水分や栄養分をとられてしまうので、そのままだと乾燥して傷みやすくなります。
芯の周りに、包丁などで切り込を入れた後、差し込んでくるっと回してくり抜き、芯をとったらぬらしたキッチンペーパーをくり抜いた穴に詰めましょう。
新聞紙かキッチンペーパーで包み、ポリ袋に入れて袋の口を軽く閉じます。
野菜室で保存するようにしましょう。
カットしたキャベツの保存
カットしたキャベツはそのままだと切断面からの水分の蒸発が進み、傷みも早くなります。
水分が抜けにくいように切断面をしっかりとラップに密着させ、全体を包んで保存しましょう。
白菜
白菜の選び方
丸ごと買う場合は、持ったときにズシリと重いものを選びましょう。
葉先までかたく巻きがしっかりしていて、上部を押すと弾力があるもの、底面の切り口が白いものが新鮮です。
中の葉先まで白い物より、黄色みを帯びている物がおすすめです。
半分や4分の1にカットされているものは、断面が平らなものを選びます。
ハクサイは切ってからも成長を続け、時間と共に断面が膨らんでくるので、膨らんでいる物は時間が経っている証拠です。
賞味期限
- そのままを常温保存:3〜4週間
- カットした白菜:ラップに包んで冷蔵庫で保存。傷みやすいので早めに使い切るか冷凍保存する。
- 冷凍保存:1ヶ月
保存方法
丸ごと保存する場合は新聞紙に包んで、冷暗所に立てて保存しましょう。
カットした白菜は傷みやすいので、ラップで包んで冷蔵庫で保存し、早めに使い切りましょう。
芯の部分を残したまま保存するメリットは、洗う時に白菜がばらけないことです。
使い切れない場合は、ざく切りにカットしてからジップロックに入れて冷凍保存すれば、1ヶ月持ちます。
白菜をバランスよく使う方法
外葉からはがして使うこともできますが、最後は白い部分しかなくなってしまいます。
バランスよく使うには、芯に切り込みを入れて1/2、1/4と割いて使うのがおすすめです。
洗う際は芯の部分から軽く水をかけ、葉先は水をはったボールで優しく洗います。
ナス
ナスの選び方
へたのトゲがとがっていて、切り口が白いものが新鮮です。
果皮の色が濃く、表面はなめらかでキズがなく、ツヤ・ハリのあるもの、全体的に丸みを帯びていて重みがあるものを選びましょう。
ナスは水分が多いため、古いものは中がフカフカしています。
賞味期限
なすの最適温度は10から12℃とやや高めなので、野菜室で保存します。
なすは温度が低い冷蔵庫で保存すると、低体温症を起こしやすいので注意しましょう。
野菜室での保存で、3〜4日以内が目安です。
保存方法
野菜室で保存する際、水分を逃がさず冷やしすぎないために、1個ずつ新聞紙に包んでビニールやラップに包んで保存しましょう。
そのまま冷蔵保存すると見た目が悪くなり、皮が茶色くシワシワになり、みずみずしさも失われてしまいます。
ピーマン
ピーマンの選び方
ヘタの部分の緑が鮮やかで切り口がみずみずしいもの、黒く変色していないものを選びましょう。
果皮の表面がツヤツヤしてハリがあり、肉厚なものが美味しいピーマンです。
カラーピーマンも同様に選びましょう。
賞味期限
冷蔵保存で2〜3週間持ちます。
切ったものでは、2〜3日で食べ切りましょう。
保存方法
ピーマンの保存温度は10℃程度です。
温度が上がらなければ常温での保存が可能ですが、通常は冷蔵庫の野菜室で保存するのがおすすめです。
保存の際には、水気や湿気を避けて保存しましょう。
キッチンペーパーで1個ずつ包んでからポリ袋に入れ、密閉せずに軽く口を閉じて野菜室で保存します。
カット済みのピーマンは、ラップに包んで保存しましょう。
大根
大根の選び方
大根はまっすぐ伸びていて太いもの、持ったときにずっしり重いものを選ぶのがポイントです。
色が白くてひげ根の毛穴が浅くて少なく、表面がなめらかなもの、触った時に硬く張りがありみずみずしいものを選びましょう。
葉が付いている場合は、葉が活き活きとしゃきっとしているものが新鮮です。
カットされている場合は、断面のきめが細かく、スが入っていないかを確認します。
賞味期限
冬場の常温で約1ヶ月、夏場は約5日、冷蔵保存で1週間〜10日ほどです。
カットされている大根は冷蔵保存で、約4〜5日とやや短め。
食べきれない場合は、料理ごとにカットしたり大根おろしにして冷凍保存することもでき、その場合は約1ヶ月持ちます。
保存方法
冬場なら、冷蔵庫よりも常温保存のほうが長持ちします。
大根は葉っぱの先から水分が失われやすいので、葉っぱと身の部分を分けて保存しましょう。
葉と切り分けたら新聞紙で包み、風通しの良い冷暗所保存します。
夏場で部屋が暑くなる場合は、冷蔵保存がおすすめです。
大根に泥が付いている場合は洗って綺麗にし、3等分に切って軽く湿らせたキッチンペーパーで包み、立てて保存しましょう。
大根を冷凍保存する場合は、ジップつきの保存袋に入れ、空気をしっかりと抜いてから冷凍庫に入れます。
そのまま鍋に入れたり、炒めたりすることができるので便利です。
大根の葉の保存
常温保存や冷凍保存の場合、葉っぱは切り落としてから保存すると説明しました。
切り落とした葉っぱの保存方法は、1度洗ってから細かく刻み、フリーザーパックやタッパーにいれて冷凍するのがおすすめです。
細かく刻んだ葉を塩揉みし、緑色の汁が出てきたら流水で洗います。
水気を絞ってからラップで小分けに包み、冷凍保存用袋に入れて冷凍庫へ。
味噌汁などにそのまま入れて食べることができます。
この状態で約1カ月保存が可能です。
アスパラガス
アスパラガスの選び方
アスパラガスは穂先が締っていてまっすぐなものを選びます。
中には細い品種のものもありますが、アスパラガスの茎は太めのほうが美味しいです。
根もとのあたりまで張りがあり、太っているものを選びましょう。
切り口に水分が残り、色が鮮やかなものものが柔らかくて美味しい証です。
シワがあったり、切り口が乾いているものや茶色いものは避けます。
賞味期限
冷蔵保存で4〜5日程です。
ゆでてから冷蔵保存する場合には5〜6日、ゆでてから冷凍保存する場合、1ヶ月持ちします。
アスパラガスは鮮度が命。
収穫されてからも成長しているため、生のまま置いておくと栄養や味がどんどん落ちてしまいます。
時間がたつにつれて固くなってしまうので、購入したら保存せずになるべく早く食べるようにしましょう。
ゆでてから保存することで、早いうちにしなびてしまうことを防ぐことができます。
保存方法
冷蔵庫でそのまま保存する場合は、成長を止めるために根元を1cmほど落とします。
切り口を濡らしたキッチンペーパーで包み、ビニール袋に入れて冷蔵室で保存しましょう。
ゆでてから冷蔵庫保存する場合は、固めにゆでて、水につけて余熱をとったら水気を拭き取りすぐに冷凍保存します。
ゆでてから保存する場合は、根元を切り落とす必要はありません。
冷凍保存する場合は、固めにゆでたアスパラを使いたいサイズにカットし、保存袋の中で平らになるよう形を整えて冷凍庫へ入れましょう。
調理するときはそのまま使うことができます。
小松菜
小松菜の選び方
葉の濃い緑色で鮮やかなもの、葉が肉厚でみずみずしくピンと張っているものがよく、さらに茎が太くしっかりしているものを選びます。
葉が濃い緑色のほうが小松菜らしいしっかりした味ですが、菜独特の風味が苦手な場合には、少し色が薄いものを選ぶのも1つの方法です。
また、黄色いものは古くなっているので避けるようにしましょう。
葉が大きくそろったものがよいのですが、葉脈が発達しすぎていると歯ざわりが悪いのでできるだけやわらかいものを選びます。
やわらかい葉のものを選ぶなら、葉に丸みがあって大きすぎないものを選びましょう。
賞味期限
カットせずにそのまま冷蔵保存する場合は、3〜4日程度。
カットしたりゆでた小松菜は、2日です。
そのまま冷凍保存する場合は2〜3週間、ゆでて冷凍保存する場合は1ヶ月持ちます。
小松菜は買ってきた状態のままにしておくと、1〜2日程度でしおれてきてしまい、含まれるビタミンCの量も減ってしまうといわれています。
長持ちさせたい場合は、用途によって生で冷凍保存、もしくはゆでて冷凍保存するのがおすすめです。
保存方法
冷蔵保存する際は、湿らせた新聞紙やペーパータオルで包み、ビニール袋に入れて乾燥しないようにします。
葉先を上にして立てた状態で野菜室に入れて保存しましょう。
小松菜をゆでて冷凍保存する場合は、固めにさっとゆでます。
ゆでた小松菜の粗熱が取れたら、しっかり水気をしぼり、ジップ付きの保存袋に入れましょう。
急速冷凍させるために、できるだけ小松菜が重なり合わないように入れるのがポイントです。
冷凍のまま調理が可能です。
ほうれん草
ほうれん草の選び方
葉先がピンと張っていてみずみずしいもの、葉肉が厚く、緑色が濃いものを選びます。
茎が適度に太く弾力性あるもので、根元に近い部分から葉が密集して、ボリュームのあるものを選びましょう。
根本が鮮やかなピンク色の物が新鮮です。
根元の部分は甘みも強く、鉄分や骨を作るために必要なマンガンといった栄養素が多く含まれているので捨てずに使いましょう。
賞味期限
冷蔵保存で1週間、冷凍保存で1ヶ月持ちます。
冷蔵保存
ほうれん草は収穫後も呼吸をしていて、水分を発散しています。
乾燥を防ぐためにも、濡らした新聞紙で包んで保存するのがおすすめです。
新聞紙に包んだら、ポリ袋に入れて軽く口を閉め、野菜室で立てて保存しましょう。
冷凍保存
ほうれん草を長持ちさせたい場合は、かためにゆでて冷蔵庫で保存しておきます。
ゆでたら冷水に取って水気をよくしぼり、ラップに包んで冷凍しましょう。
4〜5㎝ほどにカットして1回分ずつの量で包んでおくと、おひたしや味噌汁の具材として凍ったまま調理できるので便利です。
自然解凍でお浸し・サラダなどに使ったり、炒め物で他の野菜に火が通ったあと、直接入れて使うことができます。
この方法で1ヶ月持ちます。
葉物は買ってきたら水揚げすると長持ちする
葉物野菜は賞味期限が短いため、明日、明後日に使う場合でも一手間加えておくことがおすすめです。
葉物野菜をシャキッとさせた状態をキープする方法があります。
ほうれん草や小松菜、春菊などの葉物などは、そのまま冷蔵するのではなく水揚げしてから保存するのがおすすめです。
ボールに水を張り、ほうれん草を入れます。
根っこを少しカットすることで(まとまってる束がバラバラにならない範囲で)、根から水分を補給させます。
ボールに水を張り根元を30分ほど浸けておいたら、水気をふき取り、湿らせた新聞紙やペーパータオルでつつみましょう。
茎から水を吸収することで葉先がシャキッとして、鮮度を長く保つことができます。
レンコン
レンコンの選び方
レンコンは、ふっくらとして太いものを選びましょう。
持った時にずっしりと重みを感じるものが水分をしっかりと保っていて、美味しい証拠です。
古くなるにつれて乾燥してツヤがなくなり、部分的に茶色いシミのようなものが出てきます。
断面が白くみずみずしいもの、穴の中が黒くなっていないものを選びましょう。
賞味期限
カットしてあるレンコンの賞味期限は、4〜5日程度です。
冷凍した場合は1ヶ月程度持ちます。
保存方法
レンコンは水の中で育っているので、極度に乾燥を嫌います。
乾燥させないように、湿らせた新聞紙で包んでからビニール袋に入れ、冷蔵室で保存しましょう。
新聞紙などで包まないまま冷蔵庫に入れると、冷気や空気が直接当たって乾燥し、賞味期限が短くなります。
空気に触れると変色による劣化の原因にもなります。
水につけて保存すると長持ちする
タッパーなどの密封容器にレンコンを入れます。
レンコンがしっかり被るくらいの水を入れ、フタをして野菜室で保存しましょう。
水は1~2日おきに替えて保存すれば、2~3週間は持ちます。
水に浸す方法でも、皮をむいたものや薄切りにしたレンコンの場合は、3日ほどしか持ちません。
また水に浸すことによって、どうしても栄養成分が流れやすくなるので、早めに食べるようにしましょう。
冷凍保存の場合
- レンコンの皮をむいて料理に合わせてカットする
- 薄い酢酸に3分ほど漬けたら、キッチンペーパーなどでしっかりと水気を取る
- 水気をとったレンコンをフリーザーバッグに入れ、しっかりと空気を抜いたら冷凍庫に入れる
酢水につけるだけでも問題ありませんが、ゆでるほうがレンコンの食感が良くなります。
使用する際は、解凍せずにそのまま調理に使うことができますよ。
煮物や炒め物に使いましょう。
ニラ
ニラの選び方
根元を持ったときに、葉先までまっすぐ立つほどハリのあるものが新鮮です。
葉が黄色く変色しているものやしなびているもの、乾燥しているものは避けましょう。
葉が濃い緑色でツヤがあり、幅が広くて厚みがあるもの、茎は太すぎず切り口が乾いていないものを選びます。
賞味期限
ニラの賞味期限は短く、3〜4日程度です。
保存方法
乾燥や水気に弱くしおれやすいので、キッチンペーパーや新聞紙で包んでだら 、さらにラップでくるむ方法がおすすめです。
冷蔵庫の野菜室で保存します。
庫内に高さの余裕があるなら、立てた状態で保存したほうがいいですが、葉が折れてしまうと栄養素が失われてしまうので保存の際は気をつけましょう。
余ったニラは水に浸して冷蔵保存すると、10日ほど持ちます。
ニラを3~4cmの長さに切り、タッパーなどの保存容器に入れて保存しましょう。
ニラが隠れるぐらいの水を入れておき、水を3日おきに取り替えます。
この方法で保存すると、買ったときのみずみずしさを保つことができます。
かぶ
かぶの選び方
かぶは、根の部分の表面につやがあり、ひび割れや傷がなく、形のよいものを選びましょう。
葉が付いている場合は、葉が青々としていているもの、茎にしっかりと固さがあるものは新鮮な証拠です。
賞味期限
冷蔵保存の場合は、葉は3日、身は1週間です。
冷凍の場合は、1ヶ月持ちます。
保存方法
かぶはスーパーで買ったらすぐに葉を切り落としておきましょう。
葉を付けた状態にしておくと、栄養分や水分が葉にいってしまうので、スが入りやすくなるので早めに切り落としておきます(葉付きの大根と同様)。
カブの葉も食べれるので、料理に使うのがおすすめです。
かぶ本体は、新聞紙やキッチンペーパーに1つ1つ包んでポリ袋に入れて、野菜室で保存します。
葉は軽く洗い、キッチンペーパーを水でぬらしてぎゅっと絞り、包みます。
ビニール袋に入れて、冷蔵庫の野菜室で立てて保存しましょう。
カットしたカブの冷蔵保存の方法は、根の皮をむき、葉も根も使いやすい大きさに切ります。
ジップ付きバッグで空気を抜いて密封し、野菜室で保存します。
冷凍保存した場合は、葉と身をそれぞれ分けて保存し(葉は軽くゆでておいてもよい)、解凍せずにそのまま調理しましょう。
煮物や汁物に使用するのがおすすめです。
ブロッコリー
ブロッコリーの選び方
鮮度のよいブロッコリーは花蕾が濃い緑色をしており、ぎゅっと密集しています。
蕾が小さく密集していて、こんもりと盛り上がった形のものを選びましょう。
茎の切り口がみずみずしいブロッコリーを選ぶのもポイントです。
ブロッコリーの茎の切り口が茶色くなったり黒ずんだりしているものは、収穫してから時間が経っているので選ぶ際に注意します。
賞味期限
生のまま冷蔵すると4〜5日、ゆでてから冷蔵すると1〜3日持ちます。
冷凍の場合は1ヶ月です。
一般的にブロッコリーは、あまり日持ちしないといわれています。
生のままで長時間おくとつぼみが開いてしまい、変色して味も香りも半減します。
新鮮なうちにゆでて密閉容器に入れて冷蔵保存し、2~3日以内に使いきりましょう。
すぐに食べない場合は、重ならないように平らに広げて保存袋に入れ、冷凍保存しておくのがおすすめです。
保存方法
生のまま冷蔵する場合、ブロッコリーについている葉を取り除きます。
その後、湿らせたキッチンペーパーに包み、ビニール袋に入れて冷蔵保存します。
冷蔵庫へ入れる際は、花蕾の部分が傷みにくいよう、茎を下側にして立てて保存しましょう。
ゆでてから冷蔵する場合は、固めにゆでるのがポイントです。
鍋にたっぷりお湯を沸かし、水の量の1%ほどの食塩を入れたら、茎のほうから先に入れて1~2分、そのあと小房を入れてさらに1~2分ゆでましょう。
ゆであがったらザルなどにあげて水気をよく切り、粗熱をとります。
水につけると、食べるときに水っぽくなるのでそのまま冷まします。
粗熱がしっかりとれたら密閉容器にキッチンペーパーを引いて入れ、冷蔵庫で保存すれば完了です。
オクラ
オクラの選び方
オクラはなるべく濃く鮮やかな緑色のものを選びましょう。
産毛がしっかりと残っているのも、いいオクラを見分けるポイントです。
切り口や部分的に茶色くなっているものや、部分的に黒いシミのあるものは鮮度落ちている可能性があるので避けてください。
小さめのほうが味は美味しく、大きすぎると育ちすぎて苦味が出始めてしまうので小ぶりの選ぶのが無難です。
柔らかく弾力があるものを選びましょう。
オクラの賞味期限と保存方法
オクラは低温と乾燥に弱いので、ポリ袋や新聞紙に包んで冷蔵庫の野菜室で保存しましょう。
冷凍する場合は固めにゆでて水気をきり、保存袋などに入れて冷凍します。
オクラを炒め物などに使う場合は、生のまま冷凍することができます。
<オクラの下ごしらえについて>
オクラは板ずりをすることで、表面の産毛がとれて食感がよくなります。
見た目も鮮やかになり、汚れをとることもできますよ。
まな板にオクラをのせて塩を全体にふり、手のひらで軽くおさえながら転がします。
塩適量を手にとり、オクラのうぶ毛をこすり取るようにして、全体を塩でみがく方法でも大丈夫です。
豆苗
新鮮な豆苗の選び方
お店で豆苗を選ぶときは、葉が濃い緑色で、黄色くなっていないものを選びましょう。
茎がしっかりしてみずみずしいもの、根が白く弾力がありそうなものが新鮮です。
賞味期限
未開封のパックのまま冷蔵保存は、2~3日ほどです。
水につけて野菜室で保存する場合は、1週間から10日ほど日持ちします。
冷凍保存の場合は、1ヶ月が目安です。
保存方法
豆苗を使わずにそのまま保存すると、2〜3日ほどしかもちません。
すぐに使わない場合は、水にひたして野菜室で保存するか、水気をとってからフリーザーパックに入れ、冷凍保存するようにしましょう。
チルド室など冷気の強い場所で保存しないようにしましょう。
そのまま保存する場合
豆苗のパッケージを未開封のまま保存する場合には、冷蔵室か野菜室に立てた状態で保存します。
横置きや平置きにすると、葉が擦れて傷みやすくなり、さらにどんどん状態が悪くなるので注意しましょう。
水に浸して保存する場合
日持ちさせたい場合は、根を切り取った豆苗を保存容器に入れ、水をひたひたに注ぎ、蓋で密閉して冷蔵庫か野菜室に入れます。
3日おきに水を取り換えるのを忘れないようにしましょう。
庫内での乾燥を防ぐこと、密封することが長持ちのポイントです。
冷凍保存の場合
冷凍保存する場合は、豆苗の根元を切り落とし、軽く水洗いしてキッチンペーパーなどで水けを拭き取ります。
冷凍用保存袋に平らになるように入れ、空気を抜いてから口を閉めて冷凍庫へ入れましょう。
冷凍した豆苗は調理するとき、解凍せずに炒め物や汁物に使用したり、解凍してから水分を絞り、和え物やナムルにすることができます。
にんにく
にんにくの選び方
茶色いにんにくは酸化が進んでいる可能性があるので、なるべく真っ白なものを選びましょう。
ふっくら身が詰まっていて重たいもの、上端部がキュッとしまっているものを選びます。
重たいものを選ぶ理由は、水分や養分がたっぷり詰まっているからです。
上端部がぱさぱさと崩れていない新鮮なものを選ぶのがポイントです。
にんにくの適温は0度〜6度
にんにくの保存に適した温度は0度〜6度。
鮮度を保つためには、冷蔵庫での保存が無難です。
皮をむかずに1片ずつキッチンペーパーに包み、保存用の袋に入れてましょう。
食品が凍る直前の温度で保存が可能なチルド室を利用すると、1〜2ヶ月間は芽が出ることなく保存できます。
にんにくは湿気に弱いので、キッチンペーパーか新聞紙などで包んでから袋に入れると、カビの発生を防ぐことができます。
皮をむいたり、切ってしまったにんにくは、保存期間が短くなるので、ラップで包んで早めに使うようにしましょう。
冷蔵保存の場合は約1週間です。
しょうが
しょうがの選び方
根ショウガは、表面にツヤとハリがあり皮に傷がなく、ふっくらと大きな塊のものを選びます。
小さく細い物は繊維質が多いので避けましょう。
切り口がしなびていたり、変色しているものは避けますが、乾燥している場合でも切り口を薄く切ればまだ使うことができます。
黄金色で見た目に色が均一なもの、しま模様が等間隔なものが美味しいしょうがです。
形はいびつでも問題ありません。
賞味期限
常温保存で2週間持ちます。
まるごと水に浸して冷蔵保存する場合は、1ヶ月です。
使いかけの生姜も水に浸した状態で冷蔵保存すれば、1ヶ月持ちます。
生姜は常温保存が向いていますが、水に浸して冷蔵保存するほうが長持ちします。
冷蔵保存の場合、温度が低すぎない野菜室で保存しましょう。
水は3日に1度取り替えるようにします。
保存方法
生姜を保存する最適な温度は12〜15℃程度で、湿度は65%ほど必要といわれています。
生姜は元々、熱帯地域で育ってきたこともあり、寒い環境での保存に適していません。
そのため、冷蔵庫よりも常温での保存が適していますが、暑い時期などの場合には野菜室で保存しましょう。
低温で湿度の低い冷蔵庫での保存は生姜が傷む原因となり、日持ちさせることは難しくなります。
常温保存の場合は、新聞紙などにくるみ冷暗所で保存します。
もしくは、皮をむかずにタッパーに水を浸して入れ密閉し、野菜室で保存しょう。
3日に1回ほど水を交換しながら保存すると、1ヶ月ほど持ちます。
使いかけの生姜は、すっぽり浸るくらいに水を入れて野菜室で保存し、同様に水を3日に1度入れ替えます。
すりおろしやみじん切りはすぐに酸化して茶色に変色してしまうので、早めに作業を終わらせて冷凍庫に保存しましょう。
みじん切りやすりおろした生姜の冷凍保存は、1ヶ月日持ちします。
しそ(大葉)
しその選び方
しそは葉の緑色が濃く、みずみずしいものを選びましょう。
葉先がピンとしていて、葉や切り口が変色していないものが新鮮です。
賞味期限
冷蔵保存で2週間、冷凍保存で1ヶ月持ちます。
保存方法
大葉を冷蔵保存する場合は、瓶などの容器に水を入れて大葉の根元が水がつかるようにして保存します。
葉の部分が濡れると黒っぽくなり、痛むので葉に水がつかないようにするのがポイントです。
冷蔵庫で保存し、2〜3日に1度は水を取り換えるようにしましょう。
冷凍保存の場合は、1枚ずつ重ならないようにラップで包むか、千切りなどにして保存袋に入れます。
水気をしっかり取ることで、変色を防ぐことができます。
きのこ類
<きのこ類の保存のポイント>
きのこは収穫してからも呼吸をしているので、未開封のままパックに保存しておくと内部に水滴がついてカビの原因になります。
長持ちさせるには、湿気をできるだけ防ぐことがポイントです。
きのこをキッチンペーパーでくるみ、保存袋に入れて保存しましょう。
この方法で保存すれば、1週間ほど持ちます。
きのこは洗うと風味が失われるので、汚れが気になったら湿らせたキッチンペーパーで取り除くのがおすすめです。
しめじの選び方
カサの色が濃く、小さめで開きすぎていないもの、しまりがあって軸のかたいものを選びましょう。
カサに弾力がなくなり、全体が柔らかくなっているものは鮮度が落ちているので避けます。
袋の内側に水滴のついているものは新鮮でない可能性があるので注意しましょう。
しいたけの選び方
しいたけは、肉厚で丸みがあり、巻き込みが強いもの、カサがあまり開いていないものを選びましょう。
表面に傷がなく、カサの裏側が純白なもの、軸が太くて短いものがおすすめです。
調理する前に、1時間ほどカサの裏側を上にして日光に当てると、しいたけの成分がビタミンDに変化してうまみが増します。
まいたけの選び方
カサが肉厚でしっかりしているもの、軸が白くてシャキッとしているものを選びます。
触るとパリッと折れそうなものが新鮮です。
逆に、茎の部分が湿っぽくしなびていたり、酸っぱい匂いがし始めたりしたら鮮度が落ちている証拠なので注意します。
古くなるにつれ、パックの表面に水分がにじんできます。
パックで買うときには、小房に分かれた寄せ集めではなく、一株にまとまっているものを選びましょう。
えのきの選び方
背丈がそろっていて色白のもの、軸がピンとハリのあるもの、カサが開いていないものを選びます。
古くなるにつれ黄色みを帯び、締まりがゆるみ全体がバラけた感じになります。
他のきのこ類と同様に、袋に汗をかいているものは傷んでいるか、傷む寸前なので避けましょう。
エリンギの選び方
カサの色が薄い茶色で開きすぎていないもの、軸が白くて太く、弾力とかたさがあるものを選びます。
パック入りのエリンギの場合は、内側に水滴がついていないかを確認しましょう。
マッシュルームの選び方
マッシュルームは、丸くてかさの表面がすべすべしていて割れていないものを選びましょう。
また、触ったときにかたくてしっかりしているもの、色が黒くなっていないものを選びます。
軸が太く短いもの、切り口が変色していないものを選ぶのもポイントです。
マッシュルームは、日数が経っているものは軸が伸びてきます。
まとめ
この記事では、よく使う野菜の選び方や保存方法について紹介しました。
野菜の選び方や保存方法を覚えるのは大変に感じるかもしれませんが、繰り返し確認していくうちに見なくても判断できるようになります。
| おすすめ度 | |
|---|---|
| おすすめのポイント | 独自に分析した業界や企業事情の提供が面接で役立つ |
| 特徴 | 転職支援実績No.1 |
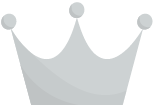 dodaエージェントサービス
dodaエージェントサービス| おすすめ度 | |
|---|---|
| おすすめのポイント | 転職者の強みや人柄を企業にアピールできる支援が手厚い |
| 特徴 | 転職者満足度No.1の実績 |
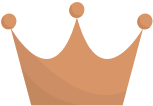 マイナビジョブ20’s
マイナビジョブ20’s転職者はこれまで自分でも気づかなかった隠れた強みを知ることができ、どのような仕事が合うのかを客観的に知ることができます。
| おすすめ度 | |
|---|---|
| おすすめのポイント | 適性検査で自分に向いている仕事に出会える |
| 特徴 | 20代専門の転職エージェント |





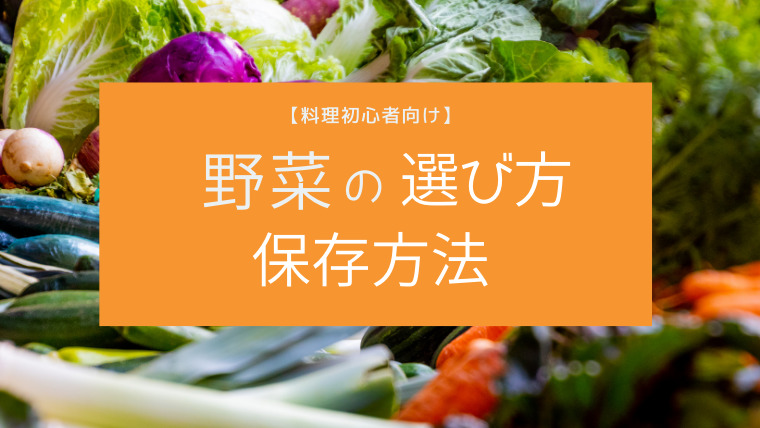

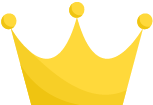 リクルートエージェント
リクルートエージェント