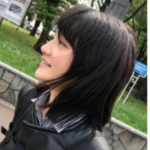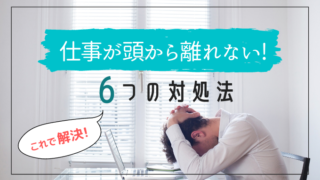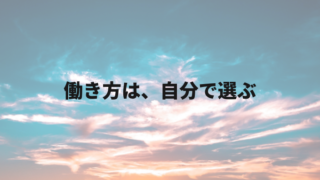こんにちは、キャリアコンサルタントのつばめです。
今回は
- クレームを受けてから、接客が怖くなってしまった人
- 次にクレームを受けるのが怖い人
に向けて記事を書いていきます。
私自身、接客業をしていたのですが、クレームを受けた時には恐怖を感じたことが何度もあります。
その度に、「次にまたクレームがきたら嫌だな〜」と思っていました。
しかし、接客業ではクレーム対応がいつ起こるかわかりません。
今後万が一、クレームで戸惑ってしまったら、無理をせずに周りに助けを求めることが大切です。
その時に備えておけると、仕事でも気持ちが楽になりますよ。
contents
クレームが怖いのは、過去のトラウマが原因
クレームが怖いと感じるのは、「過去のトラウマ」から生まれます。
私はクレームを受けた時に、「自分だけが悪い」と感じて落ち込むケースがありました。
しかし、お客様からの指摘は会社への不満が原因であることが多いです。
たとえ、あなたの対応に意見をぶつけられても、全てあなたの責任になるわけではありません。
お客様から怒られることが「怖い」と感じている場合は、まずは過去の出来事を捉え直すことから始めてみましょう。

向き合うことが怖いなら、無理して克服する必要はありません。
働き方を変えたいなら、今のうちから転職のプロに相談しておきましょう。

接客業でのクレームは1人で解決しようとしない
クレームを受けるのが怖くなってしまうのは、あなたが全てを背負おうとしてしまっているからです。
お客様からご意見をもらった時、自分1人で解決しようとするとプレッシャーに感じてしまいませんか?
クレームは発展すると、1人で解決が難しい場合がほとんどです。
お客様がお話いただいたことの事実確認が必要だったり、もし対応に不備や不満がある場合は担当スタッフに確認が必要だからです。
「1人でなんとかしなきゃいけない」と思い込まずにいれば、気持ちも楽になります。
ここを押さえておけば接客業でのクレームは怖くない
クレーム対応は、1人で対処しないでいい代わりに、適切にエスカレーションすることが大切です。
エスカレーションとは、上司の指示を仰ぐことです。
ここでは、具体的な方法を順を追って紹介していきます。
冷静にお客様の話を聴く
クレームを受けると、すぐに上司を呼びにいきたくなってしまうときもあります。
ですが、お客様からすると、話を聴いてもらえずに責任を人に押し付けているように受け止められてしまいます。
まずは、冷静にお客様の話を聴いてあげることも大切になってきます。

お客様への謝罪は、部分謝罪にする
クレームを受けた際は、お客様に対して「申し訳ございません」と連呼してしまいがちです。
しかし、お客様が話していることが全て事実であるとは限りません。
怒りの感情は時に、無理な要望に発展する場合もあります。
お客様自身も、何を言っているのかが分からなくなることもあるのです。
確認せずに全面的な謝罪をしてしまった場合、こちらが全て悪いと認めたことになってしまいます。
まずはお客様に「不快な思いをさせてしまったこと」に対して、部分的な謝罪を心がけましょう。
例を一つ挙げてみます。
買ったばかりの服なのにすぐにほつれてしまい、「不良品だ」と言うお客様が来店されたとします。
部分謝罪をするときのポイントは、下記の通りです。
- 「不良品かどうか」は事実確認する必要があるため、あえて触れない
- お客様に「買ったばかりにも関わらず、ご不快な思いをさせてしまい申し訳ございません。」と伝える
このように、ただ「申し訳ございません」と言うのではなく、不快な思いをさせてしまったことに対して謝罪するようにしましょう。
お客様からしても、何に対して謝罪されているのかが明確になるため、怒りが落ち着いてくる場合があります。
お客様の主訴と要求をつかむ
クレーム対応では、接客側とお客様側のコミュニケーションの齟齬を無くしていくことが大事です。
上司へのエスカレーションの際、お客様が意図していた事と異なると事を報告してしまうと、さらにクレームを発展させてしまうことになりかねません。
お客様が何に怒っているのか(主訴)と、どうしてほしいのか(要求)をつかむことを心がけましょう。
話を聴く上で、ポイントがあるので整理していきましょう。
主訴とは?
主訴は、お客様が不満に思っていることであり、クレームになったきっかけです。
ここでの例でいうと、「買ったばかりの服なのにほつれてしまったこと」が主訴(不満)になります。
要望とは?
要望は、お客様がクレームで要求していることです。
要求は同じ状況でもお客様によって異なります。
そのため、こちらで決めつけずに「お客様は何を求めているのか」を注意深く聞いていくことが大事です。
例を見ていきましょう。
商品の不備があった場合です。
お客様は「どう対処して欲しいのか」という観点で話を聴く場合、4つのパターンが予想できます。
- 新しい商品なのに、なぜ糸がほつれてしまったのか原因を知りたい
- 買った商品を直してほしい
- 違う商品に交換してほしい
- お店の商品自体に信用を失い、返品を希望している
などが挙げられます。
主訴と要求が理解できたら、それが本当にお客様が思っていることと合っているかを確認することも大事です。
ここを怠ると、お客様が期待していた結果と異なってしまい、二次クレームに発展してしまう可能性もあります。
主訴の確認方法
→「新しく買ったばかりにも関わらず、(洋服の)糸がほつれてしまったことに1番ご不満を感じたのですね」
その後、不満にさせてしまったことへの部分謝罪。
要求の確認方法
→「商品を返品されたいというご希望なのですね」
要求が確認できたあと、判断が1人で難しい場合には、上司への相談が必要です。
ここで曖昧に「できる」と伝えてしまうと、できなかった場合には取り返しがつかなくなってしまいます。
以前、私は「同じ商品で新しいものがほしい」という要求に応えられると思い、「できると思います」とお客様に伝えたことがあります。
結果的には、商品は用意できたのですが、型番が古くて取り寄せができない可能性があったのと、商品の状態がどれも古いせいで「またクレームに発展する可能性がある」事態になってしまい、最後までヒヤヒヤしてしまいました。
自分で自分の首を絞めることにもなりかねないので、対応方法は周りに確認をしてからにしましょう。
お客様への伝え方は、「私ではお答えが難しいため、お客様のご希望を上の者にお伝えさせていただくことは可能でしょうか」とお伝えしましょう。
また、電話の場合は改めて期日を決めてお客様へご連絡するほうがいいです。
上司や先輩に相談の際、保留が長いとお客様を待たせしてさらにイライラさせてしまうからです。
報連相の仕方を身につける
報連相の重要性
上司へのエスカレーションには、事実やお客様の不満を正確に報告する必要があります。
二次対応が必要な場合、クレームを終息させるためにも報連相が上手くできるかが大事となってくるからです。
5W1Hを意識する
報連相するときには
いつ(When)
どこで(Where)
だれが(Who)
なにを(What)
なぜ(Why)
どのように(How)
を意識することで、迅速に話を伝えることができます。
先に結果を伝えることを意識しましょう。
例に挙げたものであれば、下記のように報告することができます。
「店長報告があります。
今、お客様から電話でクレームを受けました。
先週お店で買ったばかりの商品がほつれてしまったことにお怒りで、商品を返品したいというご要望です。」
結果を先に伝えて、簡潔に報告することで伝わりやすさが変わってきますよね。
接客業でのクレームは「誠実さ」が大事
中には、理不尽なことを言って怒りをぶつけてくるお客様もいらっしゃいます。
しかしクレームはだいたいの場合、お客様が不満を抱く出来事があるからこそ起こるものです。
怒っている感情をぶつけられると怖いかもしれませんが、慣れてくると、このお客様は「何に対して不満を持っているんだろう」「(人として)役に立ちたい、解決してあげたい」という気持ちで見れるようになってきます。
そのように捉えると、お客様にも誠実さが伝わるのでクレーム対応が終了した後もお店の顧客になってくれる場合もあります。
私が尊敬する店長は、クレーム対応がきっかけで自分のお店の顧客にすることを得意としていました。
当時は、「クレームを言ってきたお客様を顧客にしなくてもいいんじゃないの」と思ってしまいましたが、今となっては理解ができました。
クレームに対して誠実な対応ができたからこそ、お客様から信頼をしていただくことができその後もリピーターになってくれていたのだと。
追記(2019/12/20):暴言を吐くお客様が急増?カスハラ被害に気をつけて
あなたは「カスハラ」というのを聞いたことはありますか?
「カスハラ」とは、カスタマーハラスメントという略です。
最近、クレームと直接関係ないことで店員に暴言を吐いたり、八つ当たりをするような理不尽なお客様が急増しています。
中には、不当な要求をして私たちを困らせてくる悪い人もいるので、ストレスを溜めてしまうケースが少なくありません。
そういった理不尽なお客様は、そもそもお店の「お客様」じゃないです。
誰が対応しても、明らかにおかしい人なので。
「ちょっとでもおかしい」と思ったら、その場で上司や同僚、先輩に助けを求めて自分の身を守りましょう。
クレームが怖い原因に少しでも心当たりがある方は、カスハラに遭ったときの対処法に目を通しておくようにしましょう。

まとめ
この記事では、クレーム対応が怖いときの対処法について紹介しました。
下記の項目がまとめになります。
- クレームは自分1人で解決しないものとわかっていると楽になる
- お客様の話を聴いて、上司に判断を仰ぐまでのスキルを身につける
- お客様の話を聴く際は、主訴と要望を整理して聴く
- 上司への報連相は結果を先に伝えて、対処方法を相談する
お客様の怒りを抑える方法や上司へのエスカレーションの方法を身につければ、クレームがきても落ち着いて対応できるようになります。
それには、慣れもあります。
もし、クレームがきたら練習だと思うくらいが気持ちが楽になりますよ。
いざクレームを受けたらこれらのポイントに沿った対応を心がけることで、冷静さを取り戻して対応ができるようになります。
ここで紹介したことを、クレーム対応ですぐに実行することが大変だという場合には通常の接客でも意識してみることがおすすめです。
買い物をするお客様の心理を知ることができ、お客様の望むサービスや販売をすることができますよ。
感謝される機会が増えたり、販売実績を伸ばすことにも繋がります。
さらにクレーム対応のコツが知りたい人は、【クレーム対応】相手の話を冷静に聴けるようになるまでに実践したことも参考にしてみてください。




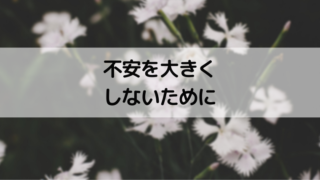

| おすすめ度 | |
|---|---|
| おすすめのポイント | 独自に分析した業界や企業事情の提供が面接で役立つ |
| 特徴 | 転職支援実績No.1 |
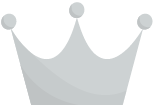 dodaエージェントサービス
dodaエージェントサービス| おすすめ度 | |
|---|---|
| おすすめのポイント | 転職者の強みや人柄を企業にアピールできる支援が手厚い |
| 特徴 | 転職者満足度No.1の実績 |
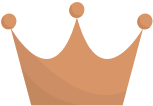 マイナビジョブ20’s
マイナビジョブ20’s転職者はこれまで自分でも気づかなかった隠れた強みを知ることができ、どのような仕事が合うのかを客観的に知ることができます。
| おすすめ度 | |
|---|---|
| おすすめのポイント | 適性検査で自分に向いている仕事に出会える |
| 特徴 | 20代専門の転職エージェント |







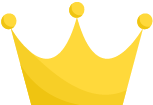 リクルートエージェント
リクルートエージェント