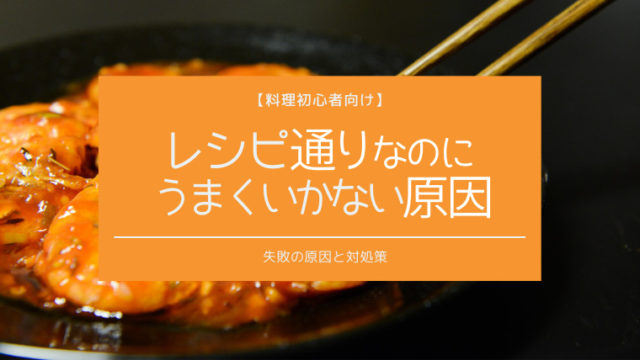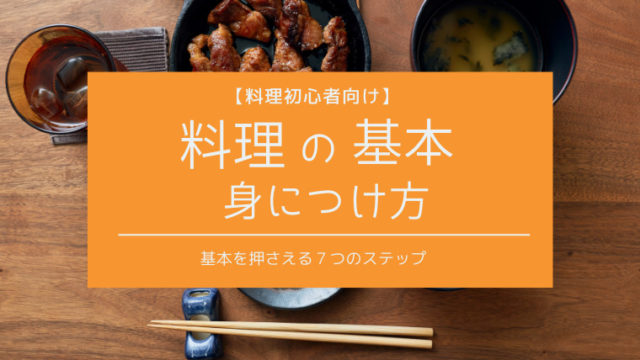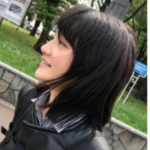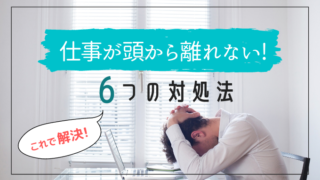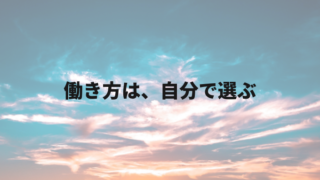「料理を上達させたい」
私自身、そう感じて約1年間本気で料理と向き合ってきました。
料理が上手になるには、基本知識に沿った調理が重要。
まずは基本のレシピに沿って作れるようにし、基本を身につけることが大事だと学びました。
ただ、いつまでもレシピを見ながら料理をしていても、レシピなしでは作れない。
そう思ってからは、できるだけレシピを暗記できるように努力し、今も料理を頑張っています。
私自身、最終的には自分のレシピを作るのが目標です。
3年前の状況から今、ある程度料理で失敗することが減り、安定して美味しい料理を作れるようになってきました。
そこで、私自身が料理初心者の頃に戻るなら「これをやるべき」という方法をまとめ、備忘録として残したいと思います。
これから「料理を上達させたい」と思う方に、少しでも参考になれば嬉しいです。
contents
料理を上達させるために、意識したきた3つのステップ
約1年間、料理を本気で上達させたいと思って取り組んだことが3つあります。
続きて良かったこと、逆に「こうしておけばよかった」と後悔することがあるのでまとめました。
1、レシピ通りに作れるようにする
料理を作る上で下ごしらえを省いたり、自分流の調理法で料理を作るとで失敗してしまいます。
私自身、アレンジを加えてしまい、料理が美味しく作れなかった経験がありました。
料理初心者の頃は、基本を覚えてからアレンジをするように心得ることが重要です。
基本をしっかり身につけるためにも、レシピ通りに作ることをおすすめします。
レシピを選ぶ時も重要で、できるだけアレンジしたもの、手が込んでいるものは避けましょう、
失敗しやすい上に、料理方法が複雑だからです。
私は、レシピ選びに結構失敗し、経験を無駄にしてきたような気がします。。
もちろん、手間暇かけたほうが料理は美味しくなるのはそうなのですが、複雑なレシピを選ぶと、予期しないところで失敗したり、工程が理解できずに間違ったやり方で作ってしまったり、自分でも失敗の理由がわかないこともあり反省が活かしにくくなります。
私のようによくわからない失敗を避けるためにも、まずは初心者向けのレシピを選ぶのがおすすめです。
私はこの本を基本に、改めて料理を作り始めました。
ネットにはレシピがあふれていますが、まずは基本となるレシピ本を決めてしまうのがおすすめ。
同じ著者さんの料理を作ることで、同じ工程を何度も繰り返すことができ、基本が身につきやすいです。
わからないこと、不安なことがあればその都度調べる
基本の手順を忘れてしまったり、アレンジしてしまうのは、「なぜそうするのか」理由がわかっていないからです。
理由を知れば、その作業は料理に欠かせないので頭に残りやすく、他の料理にも応用できるようになります。
そのためにも、1つ1つの作業に対して「行う意味」がわからない場合は、スルーせずに確認を徹底することがおすすめです。
ネットで検索すると、同じように疑問を感じる人が多いことに気づきますよ!
以前調べたことを忘れてしまっても、また調べればOK。
繰り返していくうちに、頭にしっかり残るようになります。
2、作りたい料理にどんどん挑戦する
初心者向けのレシピを何品か作れるようになると、ある程度レシピの意味を理解できるようになり、料理に慣れてきます。
ただ、私の場合は、この頃から料理に関する新しい知識をインプットするのに疲れていました。
レシピ通りに作っているつもりでも失敗することはあるし、料理を食べてもらうまでは作った料理の味に自信が持てず、毎回ビクビクしていたし、食べてくれる人が「美味しい」と言ってくれることだけが料理のやりがいだったのです。
でもそれだけだと、失敗した時に極度に落ち込むし、料理を続けるのが苦しくなる。
「もっと自分のために料理をしよう!」と思い立ちました。
この頃からは、「自分が作りたいものを作る」というコンセプトの下、新しいレシピ本を買って挑戦してみることに。
本格的なカレーやパスタ、フランス料理など、その日の気分で色々作ってみて、異なる分野の料理にどんどん挑戦。
自分が作りたいものを作れると、食べれるときにこの上ない喜びを実感します。
上手にできたときは、本当に幸せな気分になりますし。
もちろん今まで通り、人に食べてもらって「美味しい」と言ってもらえるのは嬉しいけど、美味しいものを食べれて自分も満足、というような感じ。
とにかく料理を作ることを楽しむことに重点を置き、今まで通り新しい知識は都度インプットしながら料理を続けました。
一見、料理の分野が違うようでも、料理の基本や調理法に共通点が見えて知らない間にたくさん経験を踏めているのがこの時期。
家庭料理といえば和食ですが、和食だけを最初から極めるより、幅広い料理に挑戦して作ることを楽しみ、経験を踏むのも1つの方法です。
私は、この頃から料理への関心が強くなり、好きになってきました。
私にとって飽きずに料理を続けるには、「幅広い料理を作ってみる」というのが効果的だったように思います。
まだまだ料理に関する知識が足りない時期でもあるため、「自分がどうしたら料理を楽しく続けられるか」という工夫を考えるのが大事。
「見ているだけで幸せになれるレシピ本」の効果
定番料理を作ることに少し飽きていた頃、パスタ、フランス料理など、好きな食べ物や憧れを持っていた料理に挑戦しました。
自分が作ってみたいと思うもの、興味のある料理ならなんでもいいと思います。
あとは作りたい分野の本を持つことがおすすめです。
個人的にはKindleよりも「本」派です。
中を見て、作りたいものが多く載っていれば購入して手元に置いておく。
料理をしていない時間でも、「次は何を作ろう」と見ているだけで幸せになるからです。
味付けや見た目が好みな料理家さんのレシピを作ってみる、というのもおすすめします。
3、レシピを覚えて作れるようにする
今まで、1つ1つの工程が終わるごとに、レシピを確認しては手順通りに作っていました。
そのため、「作ったことはあるけど、レシピを見ないと作れない…」というものばかりで、全く料理が上達していないと気づいたのです。
(見ながらならできるけど、自分で考えて知識を料理に活かすことは難しい段階)
レシピを見ながら作って料理が成功すると、どうしてもレシピを見ないで作ることが怖くなってしまうんですよね。
失敗が怖いからこそ、隅々まで確認したくなってしまうけど、時には大胆さ(大雑把さ)も必要。
味付けで言えば、「自分の舌」を信じることにし、レシピを頭に入れたら見ないで作ってみることに。
すると、途中で予期しない失敗をしても、過去の経験を頼りにして対処できたり、味見をしっかりすれば意外と大丈夫だったりする。
この勇気こそが、レシピを見ないで料理を作れる1歩になりました。
レシピは覚える前提で見ると、作る度に料理が上達してくるように感じます。
同じ料理を2度、3度作ることで、知識がさらに定着して料理が上手になってくる。
知識を頭で確認しながら、レシピを見なくても工程を忘れずにできるかが重要です。
私自身、まだ忘れてしまうこともありますが、このステップができるようになると、料理が気軽に作れるようになります。
もちろん、自分の好きな料理から覚えていくのがおすすめです。
基本となる味付けを覚えることを意識
何と何を合わせたらこの味付けになるのか、などを意識して作ります。
例えばてりやきのタレなら、「しょうゆ:みりん:酒:砂糖」=「2:2:2:1」など。
ソースやたれを作る時の調味料の比率を知れば、材料が違っても料理に応用できます。
割合をなんとなく覚えておくだけで、味の想像がつきやすくなり、レシピ選びにも便利です。
このステップは早ければ早いほどいいので、最初の段階でやっておくと、料理の上達がさらに早くなると思います。
また、料理を作る過程で必ずしもレシピに忠実ではなくても、自分好みの味つけが見つかったなら、それをメモに残しておくのもおすすめです。
慣れてきたら、アレンジレシピ(例:塩肉じゃがなど)に挑戦して、レパートリーを増やすこともできます。
料理を上達させるためのコツ
料理を上達させるために意識してきたこと以外にも、取り組んできたことがあります。
3つのコツがあったので、まとめました。
切り方を日々練習する
食材の切り方は、正しい方法で切れるようにすることがおすすめです。
包丁の持ち方、切り方、それぞれの方法が曖昧なら、その都度確認して毎日練習。
後になって必ず、やってきて良かったと思えますよ。
包丁の持ち方や切り方に関して、自己流でやってしまいがちですが、結局は基本に沿って行ったほうが効率的なのです。
正しい方法で練習すれば、気づいた時には早く切れるようになっています。
基本を身につければ、見た目も綺麗だし(食材も、切っている立ち姿も)、切っていて楽しいです。
味見をする
レシピ通りに作っていると、忘れがちなのが味見です。
レシピを見ながら料理をしていて、私も多々、味見をせずに料理を完成させてしまうことがありました。
うまくいくときはあっても、材料の水分や火加減、調理器具の違いから味がぶれていることも多いため、味見は大事です。
また、自分で料理を作るときにも、正しい味を「感覚で覚える」必要があります。
レシピにある「塩少々で味を整える」も、どこまで入れればいいのか疑問だったりしますよね。
何度か繰り返すうちに、どのくらいが適量なのか自分の舌が覚えてきて、足りなかったら足すということができるようになり、少しずつ感覚で覚えられました。
特に最後の仕上げが重要で、大袈裟かもしれませんが、味見の時に全神経を集中させるのです。
調味料を多く入れてしまってから濃いと思っても調整が難しいので、少しずつ加えて味を確認するというのがおすすめです。
塩以外でも、甘さが足りない時は砂糖か、みりんを少しずつ入れて調整するなど、他の料理を作る時にも、味付けが上達するように思います。
レシピ通りの分量でも味見をして、自分の舌を信じて調整できるようになりましょう。
料理ノートを作る
同じ料理を作るにも、毎回ネットで検索して味付けや料理の工程が違う…
食べる人からしても、前は美味しかったのに今回はなんか違うね、と言われていました。
毎回検索してレシピを探すのは自分も大変だし、その料理の作り方もなかなか覚えられません。
そのため、うまく作れたレシピ、今後も作りたいレシピはメモに残しておくと便利です。
繰り返し作っていく中で、自分好みにアレンジすることもできます。
また、料理を作っていて失敗してしまったこと、気づいたことなどの改善点があれば一緒に書き留めておきましょう。
味の好みが違えばそれを書いておいて、他の味付けを参考にして次回試してみることも可能です。
同じ料理を作る際は、そのメモを基に作って反省を活かせるようにします。
その結果、ただ同じ料理を作るよりも自分好みの味付けが完成されてきて、美味しく作れるようになりますよ。
メモが新しく書き換わると、それだけでも料理が上達した気がして嬉しい気持ちになります。
さいごに
私自身、まだまだ修行の途中です。
ここまで、料理初心者ながら自分で考えてなんとかやってきた感じです。
前半に紹介した、『料理を上達させるために、意識したきた3つのステップ』は「ここまでやれば大丈夫」ということは決してなく、並行することも大事だと感じています。
基本が抜けていると感じたら、「基本にもどること」を今後も意識したいです。
アレンジはそれから。
今後の目標は、もっとレシピを見ないで作れるレパートリーを増やし、いずれ自分のレシピを考えられるようになること。
それまでは、このステップを意識して頑張っていきたいと思います。
ここで紹介した料理上達への方法は、私に合った方法かもしれませんが、読んでいただいた方に少しでも何かの気づきやきっかけになったなら嬉しいです。
料理を上達させるために、一緒に頑張りましょう。
| おすすめ度 | |
|---|---|
| おすすめのポイント | 独自に分析した業界や企業事情の提供が面接で役立つ |
| 特徴 | 転職支援実績No.1 |
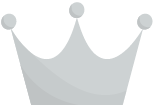 dodaエージェントサービス
dodaエージェントサービス| おすすめ度 | |
|---|---|
| おすすめのポイント | 転職者の強みや人柄を企業にアピールできる支援が手厚い |
| 特徴 | 転職者満足度No.1の実績 |
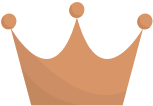 マイナビジョブ20’s
マイナビジョブ20’s転職者はこれまで自分でも気づかなかった隠れた強みを知ることができ、どのような仕事が合うのかを客観的に知ることができます。
| おすすめ度 | |
|---|---|
| おすすめのポイント | 適性検査で自分に向いている仕事に出会える |
| 特徴 | 20代専門の転職エージェント |





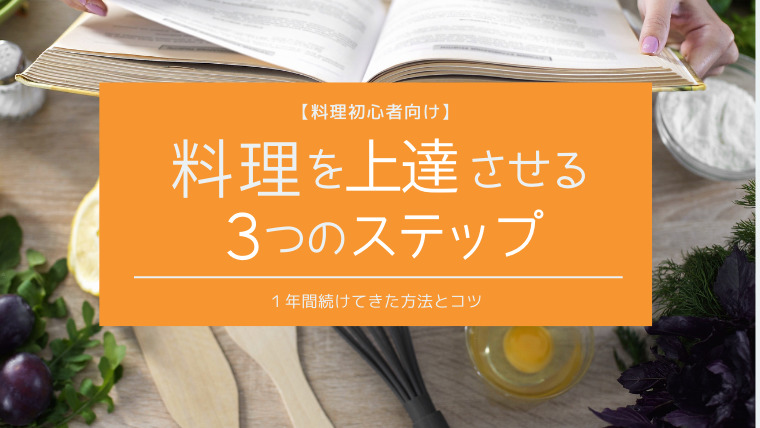


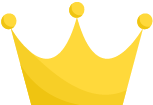 リクルートエージェント
リクルートエージェント