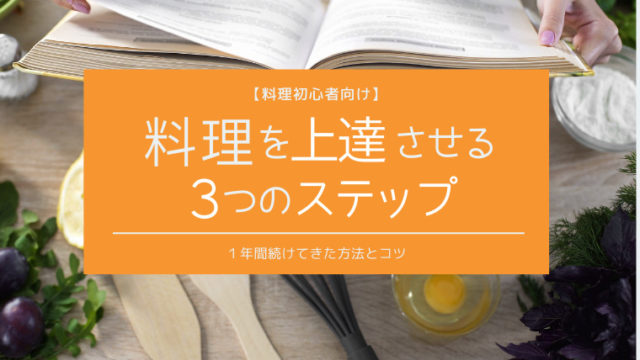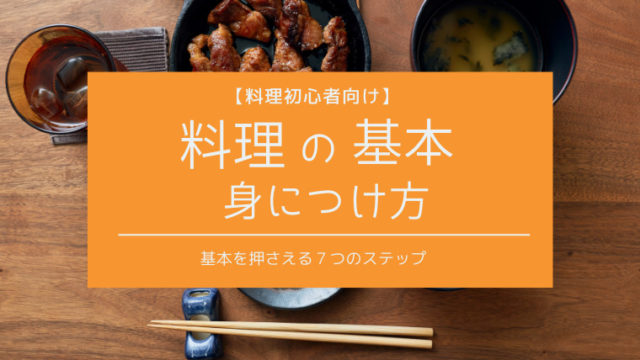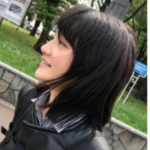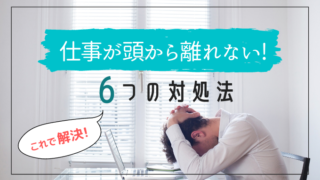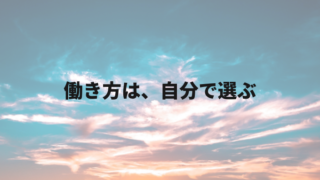「これから料理を極めたい」
「料理を始めたばかりで、まずは基本を学びたい」
こんな方におすすめの方法が、「調理法の基礎」を身につけることです。
ポイントを押さえて調理することで、レシピによって多少味つけが違っても、安定して美味しい料理が作れるようになります。
この記事では、調理法それぞれの基礎を紹介していきます。
関連記事:料理の基本知識はどう学ぶ?【初心者が身につけたい基本知識】
【7つの調理法と特徴】作るときのポイントを知ろう!
家庭料理で作られる7つの調理法の特徴とポイントを紹介します。
ポイントを押さえながら、料理のスキルアップを目指していきましょう。
焼く
焼くとは、“高温の熱”で食材を加熱する調理法のことで最もシンプルな調理方法です。
肉類・魚類を調理するのに適していて、食材そのものの味を引き立たせることができます。
焼く調理法では、素材を生かした焼き方と焼き加減がおいしさの秘密です。
同じ「焼く」でも、以下のような焼き方の種類があります。
【焼き方の種類】
- 素焼き:油や調味料をつけずに焼く方法。下ごしらえとして用いることが多い。
- 塩焼き:肉や魚などに塩をふって焼く方法。もっともシンプルな焼き方で、鮮度がいい食材に向いている。
- 照り焼き:魚や肉の調理に使われ、醤油を基本にした甘みのあるタレを食材に塗りながら焼く調理法。タレの糖分により食材の表面がツヤを帯び、「照り」が出るのが名前の由来。
- つけ焼き:たれの中に浸してから焼く調理方法。
- 蒲焼き:主にウナギに使われる調理法で、素焼きにしてから蒸し、たれをつけて焼く。サンマやイワシは蒸さずに焼く。
- 味噌焼き:味噌をつけて焼く調理法。表面に少し焦げ目をつけると香ばしくなる。
炒める
強火でサッと加熱する調理方法。
高温、かつ短時間で加熱するので、栄養価の損失が少ない点が特徴です。
炒め物は簡単に見えるのに、なかなか味が決まらなかったり、野菜炒めなどは水っぽくなってしまいがち。
野菜は水っぽいのに肉が硬くなってしまうのは、火の通り方が違う具材を一緒に炒めていることが原因です。
食材の固さに分けて炒め、最後に合わせると食感が美味しく仕上がります。
炒める時間が短縮できるので材料によっては下茹でや油通し(熱した油にを材料をくぐらせること)をしておくこともあります。
炒める調理法では、下ごしらえと味つけのポイントを押さえておくことが重要です。
味つけの準備
野菜以外の材料には下味をつける
肉や魚介類には下味をつけておくと臭みが抜け、味がなじみます。
調味料は合わせておく
味にムラができないよう、調味料は先にあわせておきます。
炒め物の仕上げ方
最後まで強火で炒める
弱火で炒めると、野菜は水っぽく仕上がり、肉や魚介類は硬くなります。
そのため、最後まで強火で炒めることがポイントです。
すぐにお皿に盛りつける
出来上がったら余熱で具材に火が通りすぎないように、早く盛りつけることが大切です。
「焼く」と「炒める」調理法の使い分け
食品の中までじっくり火を通す時に「焼く」調理法を使い、食材をかき混ぜながら高温で加熱する場合は「炒める」調理法を使います。
フライパンで加熱してステーキを作るときには「焼く」
スライス肉や細切れ肉をフライパンでかき混ぜながら加熱する場合は「炒める」
「炒める」調理法は、他の食材を一緒に混ぜて料理を作る点も異なります。
ゆでる
「ゆでる」とは、「熱湯に入れて煮ること」をいいます。
目的としては、そのまま食べるため、もしくは下ごしらえとして使う調理方法です。
素材のよさを最大限に生かせる「ゆで方」を押さえることがポイント。
熱湯からゆでる野菜
葉菜類や豆類、果菜類など土から上にできる野菜をゆでるときは熱湯からゆでます。
火の通りが早いので、『強火+短時間』で仕上げること大切です。
冷水で冷ますと、色も鮮やかになります。
水からゆでる野菜
イモ類や根菜類など土から下にできる野菜をゆでるときは水からゆでます。
火の通りが遅いので、水からゆでることで均一に火を通すことができるからです。
ゆで上がったら旨味を逃がさないために、ザルなどにあげて自然に冷ましましょう。
煮る
食材を100℃程度の調味液で加熱する調理法。
食材を調味液に浸け、火を通して味を浸み込ませます。
ゆでる調理法とは異なり、火を通すだけでなく、味を染み込ませることが目的です。
だし汁で煮たり、段階的に「さしすせそ」の順に調味料を加えたりして煮ます。
煮始めは強火が基本です。
煮汁の量
ひたひた
鍋に入れた材料が隠れないくらいの水量。
筑前煮など野菜から水分が出る料理に向いています。
最後に煮汁を煮詰める料理の場合にも最適で、味もよく染みます。
かぶる
材料の頭が水面に出ない程度の水量。
ひたひたより少し多めの水量で、食材がちょうど隠れるくらいの状態です。
途中で混ぜたり、上下に返したりできないものを煮るのに適しています。
たっぷり
食材がしっかりとひたり、湯の中でおどるくらいの水量。
材料の量に比べて水量がとても多く、材料が全部浸かってもまだ余裕がある状態のこと。
青菜や枝豆のほか、ポトフなど長時間煮る料理などに向いています。
味つけの順番と性質
味つけの基本、さ(砂糖)・し(塩)・す(酢)・せ(醤油)・そ(味噌)の順番は、押さえておきたいポイントです。
特に大事なのは、塩を入れる前に砂糖を加えること。
砂糖には食材を柔らかくする性質があるので最初に入れます。
逆に塩は、食材の水分を出して引き締める働きがあり、先に入れるとほかの調味料が染み込みにくくなるので注意しましょう。
落し蓋の役割
落とし蓋は、煮物に直接乗せるふたのこと。
煮汁が踊らないので煮崩れを防ぐことができ、少ない煮汁で味を染み込ませることができます。
揚げる
高温の油で加熱する調理方法。
揚げ物調理の場合は、200度近くまで加熱された油で調理するので、中までしっかりと火を通しながら加熱時間を短縮することができます。
その特徴から、下ごしらえとしても使います。
食材を揚げることで旨味や風味を閉じ込めたり、香味を加える効果も期待できるそうです。
食材と温度の関係
低温(150~160℃):ピーマンやししとうなどの緑色を残したい野菜、さつまいもやれんこんなど、中まで火が通りにくい野菜など
中温(160~170℃):野菜のてんぷら、唐揚げ、竜田揚げ、とんかつ、かき揚げなど
高温(180~190℃):魚介類のてんぷら、魚・野菜のフライ、コロッケなど
揚げ物の種類
素揚げ(すあげ)
素材に衣をつけずに揚げる方法。
下ごしらえに用いられることが多い調理法です。
から揚げ
素材に小麦粉や片栗粉などの粉をつけて揚げる方法。
衣揚げ
粉やパン粉、天ぷら粉などをつけて揚げる方法です。
揚げ方のポイント
①油の温度を下げない
160℃を下回るとベチャッとしてしまうので、油の温度を一定に保つことが大切です。
ある程度の油を使うと、温度が下がりずらくなります。
②余分な粉を落とす
③1度に具材を入れすぎない
1度に具材を入れる量は、鍋の表面積の1/3〜1/2までにしましょう。
それ以上入れると温度が下がりやすく、揚げ物同士がくっつきやすくなるので注意が必要です。
油の温度の見分け方
食材を揚げる前に水で濡らした菜箸を入れて、油の温度をはかります。
【油の温度の目安】
- 160℃:箸先から細かな泡が少しずつゆらゆらと上がる状態
- 170~180℃:箸全体から細かな泡がシュワシュワ出てくる状態
- 180℃以上:泡が勢いよく出る状態
和える
下ごしらえした食材に調味料をからめる調理方法。
食材には主に野菜が使れるため、ヘルシーな調理法です。
調味料は塩、醤油、みりん、砂糖、酢などを使います。
ゆでた野菜の水気をよく切り、食べる前に調味料と和えることがポイントです。
素材の味がもっとも引き立つので、できるだけ新鮮な食材を使うことも大切です。
代表的な和え物の種類
ごま和え
炒って風味を出したゴマをすり、調味料に加えて食材と和えます。
白和え
豆腐と白ゴマに調味料を加えたもので和えます。
蒸す
水を熱して水蒸気を作り、その水蒸気の熱を使って食材を加熱する調理法です。
専用の調理道具である「蒸し器」が必要になります。
水の中で加熱しないので、食材の旨みや栄養成分が流れていきません。
蒸し器内は水蒸気の対流が起きるだけなので、食材が動くことがなく、形の崩れが少ないのが特徴です。
まとめ
今回は、調理法の基本と押さえておきたいポイントを紹介しました。
それぞれの調理法の特徴を押さえることで、料理が作りやすくなると思います。
私自身、今後も料理がうまくいかないときには、調理法の基本に戻って繰り返しスキルを磨いていきたいです。
| おすすめ度 | |
|---|---|
| おすすめのポイント | 独自に分析した業界や企業事情の提供が面接で役立つ |
| 特徴 | 転職支援実績No.1 |
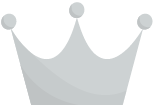 dodaエージェントサービス
dodaエージェントサービス| おすすめ度 | |
|---|---|
| おすすめのポイント | 転職者の強みや人柄を企業にアピールできる支援が手厚い |
| 特徴 | 転職者満足度No.1の実績 |
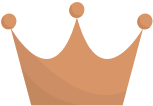 マイナビジョブ20’s
マイナビジョブ20’s転職者はこれまで自分でも気づかなかった隠れた強みを知ることができ、どのような仕事が合うのかを客観的に知ることができます。
| おすすめ度 | |
|---|---|
| おすすめのポイント | 適性検査で自分に向いている仕事に出会える |
| 特徴 | 20代専門の転職エージェント |







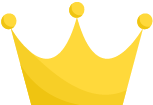 リクルートエージェント
リクルートエージェント